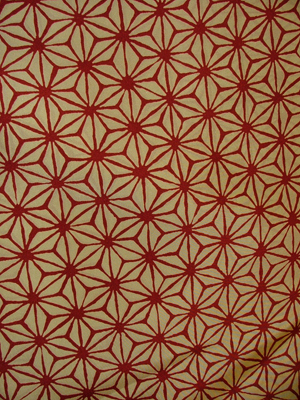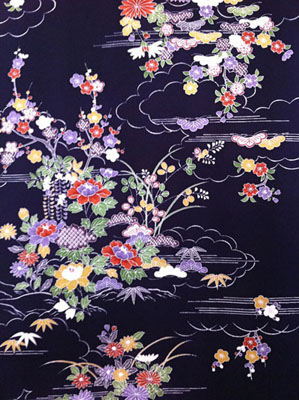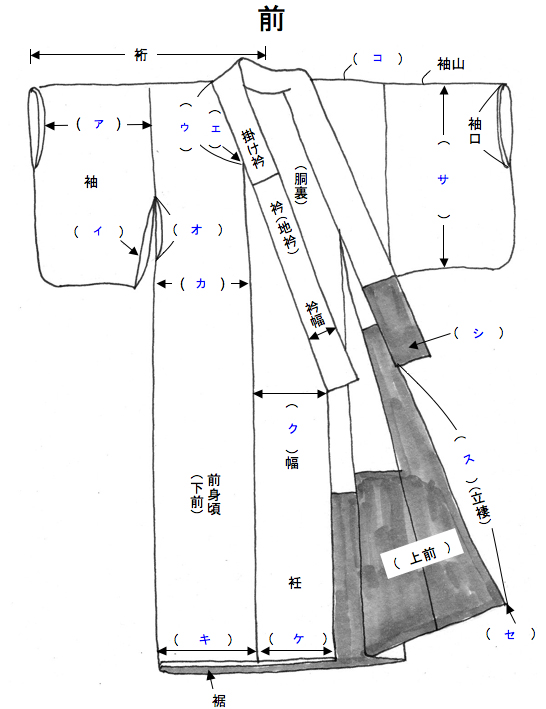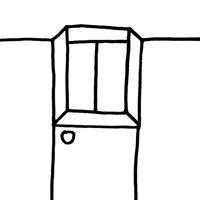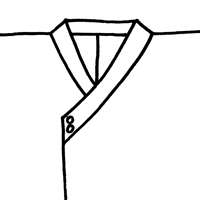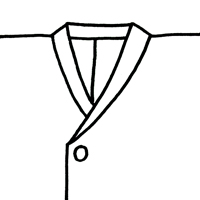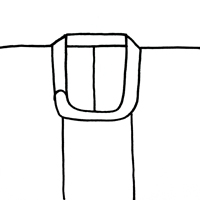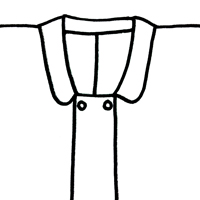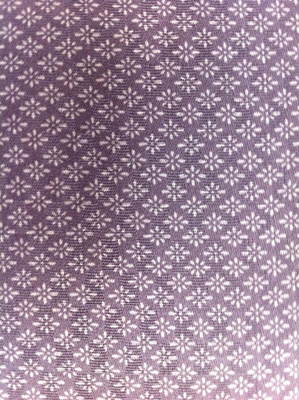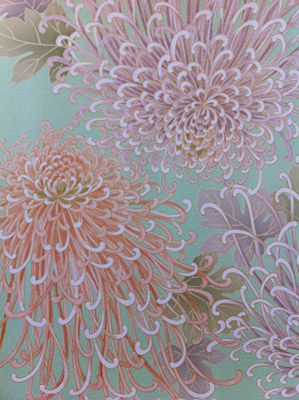問8
コートの丈について正しいものを選びなさい。
(1) 長コートはカジュアルな印象になり、また、年配には不向きです。
(2) 長コートは、着丈(長襦袢の丈)から1〜2cm引いた長さで仕立てます。
(3) 長コートはフォーマルな装いや防寒用として用いられます。
(4) 長コートはだいたい雨コートのことを指します。
問9
次のきものと帯の組み合わせのうち、間違っているものを選びなさい。
(1) 結城紬(袷)に塩瀬の名古屋帯
(2) 黒留袖(袷)に博多献上帯(金糸入り)
(3) 小紋(袷)に半幅帯
(4) 喪服に黒名古屋帯
問10
次の中で、きものの収納について正しいものを選びなさい。
(1) きものは、着用後はただちにキレイにたたんで、畳紙に入れて桐のたんすへ収納する。
(2) きものは着用後、まだ湿気のあるうちにしっかりアイロンをかけて皺をとり、その後キレイにたたんでたんすに入れ、数日後に畳紙に入れて再度たんすへ収納するとカビが出にくい。
(3) きものは着用後、衣桁かきものハンガーに吊るして一晩ほど陰干しをし、湿気をとり、汚れなどを点検してから収納する。
(4) きものは着用後、1週間から10日程衣桁かきものハンガーに吊るして日向に干し、皺がなくなってから収納する。
問11
次の中で羽織について正しいものを選びなさい。
(1) 羽織は室内でも脱ぐ必要がないので茶会に最適である。
(2) 羽織は正式な場でなければ、羽織紐なしにジャケット感覚で羽織れば良い。
(3) 羽織は裏でおしゃれを楽しむので、単衣仕立てにしない。
(4) 羽織の丈は特に正式な決まりはない。
問12
次の帯のうち、紬に締めるのに不向きな帯はどれですか。
(1) 丸帯
(2) 半幅帯
(3) なごや帯
(4) しゃれ袋帯
問13
次の帯についての記述のうち、正しいものを選びなさい。
(1) しゃれ袋帯は袋帯なので黒留袖などの礼装にのみ用いる。
(2) しゃれ袋帯は袋帯なので締める時は二重太鼓に締める。
(3) しゃれ袋帯は袋帯なので全通である。
(4) しゃれ袋帯はとてもしゃれている袋帯のことである。
問14
シミの対処方法として、正しいものは次のうちどれですか?
(1) シミは早い方が落ちやすいので発見次第、熱湯で湿らせたタオルで力いっぱい擦り取るようにして、ある程度落としてから最寄りの呉服屋さんか悉皆屋さんへ早めに持ち込む。
(2) シミは、その原因や種類によって落とし方が違うので、出来るだけ早く専門家に相談をする。
(3) シミは、ベンジンで湿らせたタオルを硬くしぼって思い切り叩くと落としやすい。
(4) シミは、赤ワイン以外は水で濡らして硬くしぼったタオルでよく叩いて落とす。
問15
二重太鼓について、次の説明のうち正しいものを選びなさい。
(1) 二重太鼓は、袋帯でお太鼓部分を二重にする結び方をいう。
(2) 二重太鼓は、帯の種類に関わらずお太鼓結びのことをいう。
(3) 二重太鼓は、男性の場合は角帯の場合のみ可能である。
(4) 二重太鼓は、太鼓橋を渡る時の行きと帰りのことをいう。
問16
帯について、次の説明のうち、正しいものを選びなさい。
(1) 昼夜帯とは、昼夜を問わず締められる帯のことをいう。
(2) 昼夜帯とは、職人が昼夜を問わず根気よく織り続けてようやく完成する帯のことをいう。
(3) 昼夜帯とは、昼と夜の光線の違いによって劇的に印象の変わる帯のことをいう。
(4) 昼夜帯とは、表と裏に違う布を用いて縫い合わされた帯のことをいう。
問17
鯨尺について正しいものを選びなさい。
(1) 鯨尺の1尺は約30cm
(2) 鯨尺の1尺は約38cm
(3) 鯨尺の1尺は約40cm
(4) 鯨尺の1尺は約44cm